|
君に恋をした。 美しく、そして薄く淡い紅色をした、君の頬・・・唇・・・。 なんて、綺麗に輝いているのだろう。 その美しい君のすべてに、口づけたい。 甘く愛にあふれた口づけを・・・・・・・ 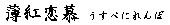 「おいで・・・私のもとへ」 他には誰もいない・・・二人きりの部屋で、友雅はそっとあかねの手をとり、自分の側へと引き寄せる。 「君にはこの色が似合うだろうと思ってね」 そう言いながら、友雅はひとつの小さな入れ物に入った、紅をあかねに手渡した。 「これは・・・?」 「紅だよ。君のその小さな口元へそっとつけるためのね」 もらってもいいんですか。と言うあかねの問いに、それは君のための紅だよ。と友雅は言葉を返す。 その紅は薄く淡い色で、とても綺麗な色をしていた。 まるで、あかねのためだけにあるような色の紅。 まさに、友雅はその紅をあかねのために特別に作らせていた。 この世にたった1つしかない特別な紅・・・・・ 「かしてごらん」 「えっ?」 友雅はあかねの手の平から、手渡したばかりの紅を手にとった。 あかねは、もらったばかりなのにどうしてだろう?と少し途惑ってしまう。 「私が、つけてあげよう」 手にした紅を、そっと右手の小指につける。 その指が、だんだんとあかねの唇へと近づいていく。 「と、友雅さんっ?」 近くなっていく二人の距離にあかねは一層、途惑ってしまっていた。 それでも気後れする事もなく、友雅の小指があかねの唇にそっと触れた。 「ほらごらん、やっぱり君にぴったりだ」 そう言いながら、友雅は近くにあった手鏡をあかねに向ける。 「えっ、これが私・・・?」 友雅の指がふれた時のどきっとした緊張も忘れて、 あかねは、ただただ自分の変化におどろいていたのだった。 「とても綺麗だよ」 紅をつけただけで、あかねは口元から色っぽく美しくなっていた。 「友雅さん、こんな素敵な紅をありがとうございます」 「喜んでくれて嬉しいよ」 あかねは、笑顔で友雅に微笑みかけている。 本当に心から嬉しそうだ・・・・・ 「私から、何かお礼出来ることはないですか」 「君の笑顔で充分だよ、あかね」 「そうですか・・・?」 こんな素敵な紅をもらったのに何もお礼が出来なくていいのだろうか。 と、少し不安そうな表情で友雅を見つめる。 「・・・そうだ」 「私に何かお礼出来る事ありましたか?」 急に何か思い付いたような友雅に、あかねは明るい表情で問う。 「君がそんなに私にお礼がしたいと言うのなら・・・」 「えっ?」 いいのがあるよ。そう言い、あかねの目の前まで近づいていく。 そしてそのまま、あかねの唇にそっと口づけをした。 「友雅さん?!」 突然の出来事に、あかねは途惑うばかりだった。 そんな彼女に友雅はこう言った・・・・・ 「君の唇が、私を求めていたからね」 その言葉に、何も言い返せなかったあかねは俯いてしまう。 そんなあかねに友雅は、さらにそっと口づけをした。 「愛しているよ、あかね」 どうしてだろう。口づけも、愛の言葉も嫌じゃない。 そんなあかね心の答えは、こうだった・・・・・ 「私もです。友雅さん」 二人のお互い恋い慕う心を1つの紅が、結びつけた。 これは不思議な縁(えにし)が二人の恋を導き始めた、ある一日の物語。 二人は何度も、何度も・・・甘い口づけを交わしている。 【完】 |
珠咲初の友あかです。何故か緊張してます。友雅さんだからかな?
ずっと考えていた、友雅さんがあかねに「紅」を贈るお話。
えっとね。最初から口づけが目的で紅をあげました。
なので、友雅さんの勝ちvなお話なんですよー。
ちょっとだけ強引な気もしますが、友雅さんだから良いのですv(040511)
ずっと考えていた、友雅さんがあかねに「紅」を贈るお話。
えっとね。最初から口づけが目的で紅をあげました。
なので、友雅さんの勝ちvなお話なんですよー。
ちょっとだけ強引な気もしますが、友雅さんだから良いのですv(040511)
←home